- 太陽光発電は雨や曇りの日には電圧はあるのか?
- どれくらい晴れの日と差があるのか?
- 雨の日や曇りの日に光吸収の良いパネルにはどんな物があるのか?
- 雨の日や曇りの日よりも大切なのは年間日射量。
このページではこんな内容を紹介していきますので、雨の日や曇りの日の発電などがわかる内容です。
晴れの日と比べると、まさかの結果に・・・。
太陽光発電のYouTube動画です。わかりやすかったので載せておきます。
ソーラーパネル(太陽光発電)は曇りや雨での発電する?

ソーラーパネルは雨や曇りの日でも発電は可能。

極端な話しを紹介すると、ソーラーパネルは月明かりでも発電する事が可能です。
ソーラーパネルの発電量は少なくなる。
ソーラーパネルは曇りの日でも雨の日でも、電圧はあると言えます。
ですが、太陽光を「光の単位」で表すと・・・
- 晴天日の太陽光の単位・・・10万ルクス。
- 月明かりの太陽光の単位・・・0.2〜0.3ルクス。
そのため、ソーラーパネルに電圧はありますが、電圧が低すぎてパワーコンディショナーは起動しません。汗。
太陽光発電を設置した方から、パワーコンディショナーが動かないと、「夜は発電してない。」と思われますが、発電は少なからずしています。

では、曇りの日や雨の日は、晴れの日と比較してどれくらいの発電量なんでしょうか?
ソーラーパネル(太陽光発電)曇りや雨で発電量は?


ソーラーパネル雨の日と曇りの日の発電量を紹介していきます。
結果は想像の上をいっているかもです。。。
ソーラーパネル雨の日の発電量は?
太陽光発電は各メーカーで発電量に少しの違いがあり、各社の発電量をチェックすると、雨の日は1/5〜1/20という数字が公表されていました。
例えばですが、100%の発電量があるとして、雨の日に換算すると5%〜20%くらい発電量がある。
・4kwの太陽光発電なら、変換効率60%として2.4kwの発電。
・4kwの太陽光発電なら、0.24kw発電。
太陽光を光の単位で換算して考えても、各メーカーが発表した数値内におさまっていますね。
雨の日では発電はできていますが、発電量が1/10くらいに落ちます.
次に曇りの日はどれくらいの発電量(電圧)があるのでしょうか?
太陽光発電 曇りの日の電圧はわずか?

ソーラーパネル曇りの日の発電量は1/3〜1/10となっていて、雨の日に比べて発電量が多い結果になりました。
晴れの日の発電量を100%としたら、曇りの日は10%〜33%くらいは発電していると各メーカーも発表しています。
また、ある情報誌からは・・・
晴天時の発電量を100%とした場合、各メーカーや性能、季節、雨や雲の程度によりますが、一般的には40%〜60%程度まで低下すると言われています。
引用元:limiaより
というような見解もあります。
太陽光を先ほどと、同じように単位で表すと・・・
- 晴天の太陽光・・・10万ルクス
- 4kwの太陽光発電なら、2.4kw発電。
- 薄曇の太陽光・・・50,000〜30,000ルクス
- 4kwの太陽光発電なら、1.2kw〜0.72kw発電。
- 曇天の太陽光・・・50,000〜10,000ルクス
- ・4kwの太陽光発電なら、1.2kw〜0.12kw発電。
引用元:照度と明るさの目安より
各メーカーが発表した数値内に、光の単位で表してもしっかりと収まっていますね。
曇りには濃い曇りと薄曇りがあるので、この違いから1/10から1/3に発電効率に違いがあり、太陽光発電を設置した時に戸惑う事がなくなります。

よくある間違いに、LED照明を太陽光発電に当てると、発電して売電できると言われる方がいらっしゃいます。
ですが、今、紹介したように照明を光の単位で表すと、500ルクス程度の光なので売電できるほどの光ではないので、間違いないようにしたいですね。
ソーラーパネル曇りで光吸収率が高いパネルとは?


ソーラーパネルには曇りや雨でも光吸収率が高いパネルが存在します。
それがCIS・CIGS系、非シリコン系のパネルです。
CIS・CIGS系のパネルはふつうのパネルより安価で購入できる事。また、光吸収率がとても高く、雨や曇りでも有利に発電可能です。
最近注目され始めているのが「CIS系」「CIGS系」の太陽電池です。非シリコン系・化合物系で影や曇りに強く、生産コストもシリコン系より安く済むので経済的というメリットがあります。
引用元:limiaより
シリコン系より薄型なのが特徴。
パネルを薄型にする事で熱がこもる事を防ぎ、熱に強いパネルと言えるのが非シリコン系のパネルです。
1/100の薄さでも、シリコン系と同じ光の吸収ができ、しかも安価!
また、従来の直列系と違い、非シリコン系は発電が途絶える事がないメリットありです。

ソーラーパネルの直列系をわかりやすく説明します。
ご自宅にある扇風機のケーブルをイメージして頂くとご理解しやすいのですが、
扇風機のケーブルの一部がないと(実際にはありえない。)電気が流れていないので、扇風機は回らないですよね。
それと同じで直列系は日陰の影響が出ると発電しません。

ですが、非シリコン系は並列のために、一部が発電できなくても発電できます。
非シリコン系は扇風機のケーブルが数本あるので、1本が発電できなくても他のケーブルが発電するイメージです。
「じゃあ、非シリコン系のパネルが最適じゃないの?」
こんな意見がでますが、非シリコン系にはこんなデメリットが・・・。
太陽光発電の光害についての動画です。
CIS・CIGS系(非シリコン系)のデメリットは?

「非シリコン系とシリコン系」の変換効率と比較すると、変換効率が悪いのがデメリットです。
「どっちのパネルがいいんだよ!」ってお思いの方もいらしゃるはずですが(;゚Д゚)
変換率をチェックしてみると・・・
変換効率にここまでの差があります。
ですが、地形や気候を考えて、非シリコン系のパネルを選ぶ場合もあり、あなたのお住まいの気候などを考慮すると、最適なパネルがわかるはずです。
当然、これから太陽光発電を設置する方は、初心者なのでシリコン系か非シリコンか悩むわけですが、優良な販売店にお任せすると適切なパネルを紹介してもらえます。
- 安価なために初期費用を抑える事。
- 曇りや雨でも発電できるメリットがある事。
- 熱に強い事。

適切なパネルを設置することで、長年にわたって発電し続けてくれますよ。
結果、売電収入が入り、電気料金が安くすみますね。

下のタイナビなら、あなたの自宅に最適なパネルを選定し、料金も格安な販売店を紹介してくれます。
太陽光発電(ソーラーパネル)年間の日射量が大切。

ソーラーパネルは雨の日や曇りの日では、発電量が低くなりますが、太陽光発電を設置するなら、年間の日射量を考えることが大切です。
年間の日射量を把握することで、意外な事実が見えてくるので、都道府県別に日射量を紹介していきます。
都道府県と順位。 1日の日射量。 年間の日射量。 1位/山梨(甲府) 4.44
4,732
2位/高知(高知) 4.4
4,690
3位/宮崎(宮崎) 4.36
4,647
4位/静岡(静岡) 4.3
4,583
5位/愛知(名古屋) 4.21
4,487
6位/岐阜(岐阜) 4.21
4,487
7位/鹿児島(鹿児島) 4.2
4,476
8位/徳島(徳島) 4.18
4,455
9位/愛媛(松山) 4.18
4,455
10位/三重(松山) 4.17
4,444
11位/群馬(前橋) 4.15
4,423
12位/和歌山(和歌山) 4.15
4,423
13位/香川(高松) 4.12
4,391
14位/熊本(熊本) 4.11
4,380
15位/岡山(岡山) 4.1
4,370
16位/長崎(長崎) 4.1
4,370
17位/北海道(網走) 4.08
4,348
18位/兵庫(神戸) 4.06
4,327
19位/沖縄(那覇) 4.02
4,285
20位/佐賀(佐賀) 3.98
4,242
21位/栃木(宇都宮) 3.97
4,231
22位/埼玉(さいたま) 3.97
4,231
23位/神奈川(横浜) 3.97
4,231
24位/長野(長野) 3.96
4,221
25位/大分(大分) 3.96
4,221
26位/茨城(水戸) 3.94
4,199
27位/福岡(福岡) 3.94
4,199
28位/山口(山口) 3.92
4,178
29位/千葉(千葉) 3.91
4,167
30位/大阪(大阪) 3.91
4,167
31位/宮城(仙台) 3.85
4,103
32位/奈良(奈良) 3.82
4,071
33位/北海道(札幌) 3.81
4,061
34位/福島(福島) 3.78
4,029
35位/岩手(盛岡) 3.74
3,986
36位/京都(京都) 3.74
3,986
37位/東京(新宿) 3.73
3,975
38位/滋賀(大津) 3.7
3,943
39位/山形(山形) 3.68
3,922
40位/福井(福井) 3.63
3,869
41位/鳥取(鳥取) 3.58
3,816
42位/富山(富山) 3.57
3,805
43位/青森(青森) 3.56
3,794
43位/石川(金沢) 3.56
3,794
43位/広島(広島) 3.56
3,794
43位/島根(松江) 3.56
3,794
47位/新潟(新潟) 3.55
3,784
48位/秋田(秋田) 3.5
3,730
都道府県別の日射量や、年間の日射量を紹介しましたが、あなたの都道府県は何位に入っていたのでしょうか?
下位の方に入っていても発電量はそれなりにあり、太陽光発電の良さがわかりますね。
太陽光発電の電力需給運用においては、需給バランスが崩れると電力の余剰や不足につながるため、 日射量データをもとにした太陽光発電量予測が大きく外れる事態をいかに減らすかが課題となっている。
引用元:人工知能学会全国大会論文集より
意外だったのは北海道の年間日射量がわりと高かった事です。
雨の日と曇りの日のまとめ。
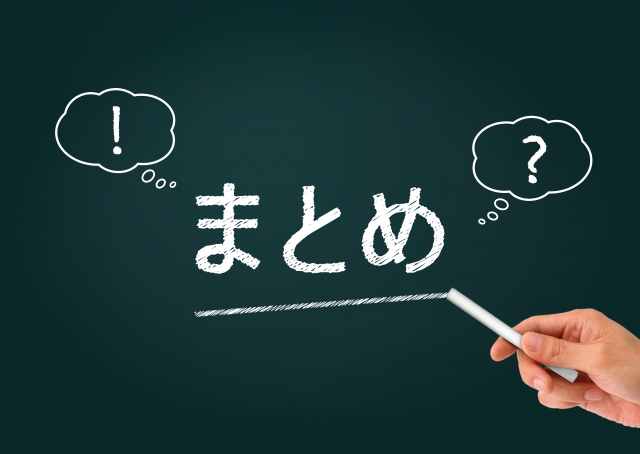
以上が太陽光発電の雨の日と曇りの日のまとめでした。
太陽光発電は雨の日、曇りの日よりも年間の発電量を考え、地形や気候に合ったパネルをお選びになる事が大切です。
あなたがしっかりした販売店に任せると、曇りでも雨でも発電効率の良いソーラーパネルを紹介してもらえます。


本日はここまでお読み頂きありがとうございました。
ハツオでした!
ツイート




